保育園入所と支援体制の現状/議会報告
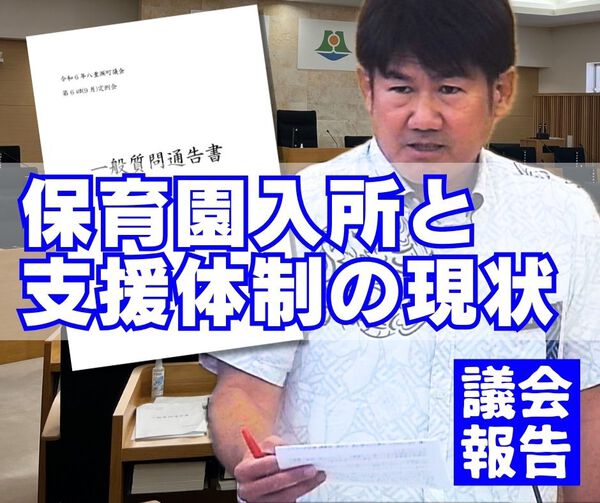
9/24に行った議会定例会一般質問では、7項目について質疑しました。今回は「保育行政について」を報告します。
 年度途中入所、兄弟姉妹同一入所について
年度途中入所、兄弟姉妹同一入所について■質問/年度途中での保育園入所希望に対し、どのように対応しているか?
■答弁/保育園への入所は、毎月1日からの入所を基本とし、入所希望月の2ヶ月前の月末を申請期限として受け付けている。待機児童を含め、保育の必要性が高い方から順に入所案内を行い、入所希望月の前月中旬頃には、空きがある施設への案内を行っている。ただし、虐待やDVの恐れがあり社会的養護が必要な場合には、締め切りに関係なく、月の途中でも優先的に入所案内を行っている。
■質問/保護者や保育園から「空きがあるにもかかわらず、入所まで2か月待たされている」という声があるが、改善の余地はないか?
■答弁/0歳児の場合、生後6ヶ月後からの入所となるため、当初は空きがあるが、4月以降になると、毎月およそ30名の途中入所希望者があり、入所判定に時間を要する。例えば、10月1日に入所を希望する場合、8月末が申込期限となり、その後入所判定を実施し、9月中旬に入所案内が行われる流れである。保護者には早く入所させたい気持ちがあることは理解しているが、ご了承いただきたい。
■質問/兄弟姉妹を同じ保育園に入所させたいという希望に対し、どのように対応しているか?
■答弁/兄弟が同時に入所を申請する場合の加点はないが、既に兄弟が入所している園への入園を希望する児童には、調整時に加点している。同点の場合は、兄弟児が既に入所している方が優先される。ただし、空きがない場合には別の保育園を案内している。同一入所できている割合は約8割である。兄弟優先のニーズは理解しているが、優先しすぎて、保育の必要性が高い方が入所できなくなることは避けなければならない。0歳児に関しては比較的空きがあるため、その場合は希望に応えられることも多いと認識している。
—-------
保育園への入所は、保護者の就労状況や家庭環境などを審査・判定の結果、保育の必要性の高い方から入所とすることとなっています。公平な入所判定のためにも必要な判定機関であることは理解できました。
しかし、申し込み時期を逃してしまうと希望する入所時期から遅れてしまうことになるので、保護者への適切な情報提供でご理解ご協力を得ながら、スムーズな入所対応と保育園とも共有を十分に図るよう求めました。
—-------
 加配保育の実施状況
加配保育の実施状況■質問/加配保育の実施状況について、現在の体制や支援内容について伺う。
■答弁/令和6年9月時点で、特別な支援を必要とする52名の児童に対し、発達や特性に応じて32名の加配保育士を配置し、安全で安心な保育を提供している。各保育園やこども園において特別支援保育事業を活用し、加配保育士の配置や支援児童の数に応じて補助金を交付している。また、心理士が園を巡回して相談や助言を行ったり、必要に応じて発達検査の実施や保護者への助言を行っている。
■質問/加配保育の現場から「保育士が足りない」という声が上がっているが。
■答弁/補助金が少なく保育士が確保できないという園もあれば、補助金を活用して保育士を確保し受け入れている園もある。この補助事業は町の単独事業として実施しているが、他市町村と比較しても本町の補助額は若干高いと認識している。今後、他市町村の状況も確認しながら、補助のあり方について検討していきたい。
—-------
現状でも受け入れができている法人保育園もあるということですが、特定の園に偏らないよう配慮が求められます。
卒園後の小学校での対応も必要になってくるので、住み慣れた地域にある保育園に通園できて、安心して進学できるよう、保育園との連携を深め、加配保育事業をさらに充実させながら、環境整備を進めていくことを求めました。
—-------
 土曜日の家庭保育について
土曜日の家庭保育について■質問/土曜日の家庭保育について、町と園長会の連名で保護者に協力を求めた件の現状について伺う。
■答弁/八重瀬町長と園長会会長の連名で家庭保育の協力をお願いした経緯は、保育士不足や待機児童の増加、保育士の処遇改善が求められていたことが背景にある。また、園長会からの要望もあり、土曜日に家庭保育の協力をお願いする通知を保護者に出した。しかし、現在はある程度待機児童が解消され、保育士の確保や処遇改善も進んでいるため、町長名での土曜日の家庭保育の依頼は行っていない。
—-------
一時期の待機児童問題は、保育所の増設や公立保育園のこども園への移行、保育士の処遇改善などの取り組みと、保護者の家庭保育への協力により解消傾向にあります。このような取り組みは、関係者の協力を高く評価できるものだと感じています。
しかし、未だに「かくれ待機児童」の問題も指摘されています。また、今後、少子化が進む中で、保育所の運営をいかにして保育の質を維持しつつ安定的に続けていくかが課題です。保護者や幼児の多様なニーズに柔軟に対応し、安心して子育てができる環境を整えていくことがますます重要になります。
預かる側(保育園や保育士)、預ける側(保護者)ともにしっかりと連携し、ニーズをしっかり捉えた子育て行政を今後も進めていただくことを期待しています。
—-------
今後も、町民の皆さんの声を反映させながら、より良い保育環境を整えていきたいと思います。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。







